第46回九都県市合同防災訓練から学ぶ
- 協働型災害訓練事務局
- 2025年11月5日
- 読了時間: 2分

先日、9月7日(日)に県営権現堂公園2号公園で開催された「第46回九都県市合同防災訓練(埼玉県会場)令和7年度埼玉県・幸手市総合防災訓練」は、大規模な災害に備えるための重要な機会となりました。今回は、この訓練から得られる気づきを、福祉施設で働く皆さんと共有したいと思います。訓練では、航空機による情報収集から、建物からの救出、応急救護所の開設・運営など、多岐にわたるシナリオが実施されました。また、防災フェアでは、災害時の備蓄品や最新の防災技術が展示され、一般来場者が体験できるコーナーも多く設けられていたようです。
このような訓練は「公助」と呼ばれる、行政や消防、警察といった公的機関による支援の重要性を改めて認識させてくれます。しかし、災害時には公的な支援がすぐに届かないことも想定しなければなりません。特に、要配慮者が多く利用される福祉施設では、職員が中心となって利用者さんの安全を守る「自助」と「共助」の力が不可欠です。
今回の訓練内容を福祉施設の視点から見ると、特に以下の点が重要だと考えられます。
・情報収集と伝達の訓練: 災害時の情報網は寸断されることが多いため、携帯電話やインターネットに頼れない状況での情報収集・伝達方法を確認しておく必要があります。訓練では臨時災害放送局の開設訓練なども行われましたが、施設内では非常用ラジオや職員間の安否確認方法など、確実な連絡手段を平時から準備しておくことが重要です。
・応急救護訓練の重要性: 医療機関や救護班がすぐに到着できない事態に備え、職員全員が応急手当の知識と技術を身につけておく必要があります。訓練で行われた応急救護所の開設・運営は、福祉施設内での救護スペースの確保や、医薬品・衛生用品の備蓄計画を考える上で参考になるでしょう。
・物資備蓄の再点検: 訓練会場では、段ボールベッドや防災備蓄品などが展示されていました。利用者の特性に合わせた食料、水、医薬品、衛生用品、介護用品(おむつなど)を最低でも3日分、できれば1週間分確保しておくことが推奨されます。また、非常用電源の確保も忘れてはなりません。
私たちは、いつ起こるかわからない災害に備え、常に意識を高めておく必要があります。今回の訓練は、私たち自身の備えを見つめ直し、災害対策をより実践的なものにするための貴重なヒントを与えてくれたのではないでしょうか。
皆さんのご家庭や施設では、今回の訓練内容を踏まえて、どのような災害対策に取り組んでいくべきか。考えるきっかけになればと思います。













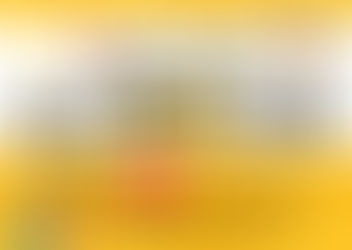







コメント